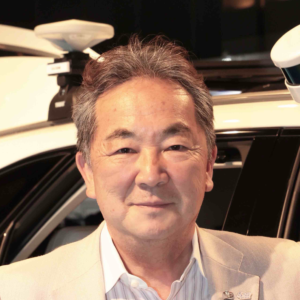「ASV/ADASって何?」と聞き慣れない言葉かもしれませんが、実は自動運転よりも身近で、とても効果がある安全機能です。前回のコラムではクルマの前後の動き(加速・減速)を自動で調整してくれるアダプティブ・クルーズ・コントロール(ACC)について説明しましたが、今回はクルマの横方向の動き(ハンドル機能)をアシストするレーンキープ・アシスト・システム(LKAS) について説明しましょう。
LKASはカメラで車線を認識し、走行車線の中央付近を維持するよう、ハンドルの操作をアシストしてくれます。ここではLKASが採用されるようになった背景について説明しましょう。

加速と減速をアシストするACCの歴史は長く、昔はオートクルーズという名称で普及していました。最近は設定速度だけでなく、前を走るクルマとの車間を自動で維持できるようになったのは、センサーの普及が貢献しています。しかし、ハンドルを自動で動かす機能は最近のことで、ハンドルの機能がモーターでアシストできるようになったことと、車線(白線)をカメラで認識できるようになったからです。
しかし、ハンドル操作は簡単には自動化できず、いくつかのステップを踏みながら進化してきました。ここでは運転者のハンドル操作の支援を「操舵支援」と呼ぶことにしましょう。
国連では操舵支援の基準は「UN-R79」として制定され、実際はユースケースごとに段階を経て実現してきました。まず、2017年に、時速10Km以下で駐車を支援することを前提としたハンドルの操舵支援、さらに車線を維持できる機能が国連基準として採択されました。
しかし、自動運転を視野にいれるともっと速い速度や車線変更でも、ハンドルの自動化の基準が必要となります。そこで第二段階として高速道路でのウインカー操作を起点とした自動車線変更や緊急時の操舵支援が2018年に採択されました。このようにハンドル操作の自動化は段階的に進化してきたのです。

ハンドルの自動化が難しい理由として、ハンドル操作は途中でやめることができないことが挙げられます。ハンドルを動かしているときにシステムに異常が発生したとき、車の挙動を急変させることなくドライバーが安全にハンドル操作を引き継げるようにする必要があるのです。その意味ではそうしたシステムのリスクも考慮した設計が求められます。
このように操舵支援という運転支援が利用できるようなったことで、ASV/ADASは飛躍的に進化し、最近では軽自動車にも普及してきました。操舵支援は、一見自動運転のように振る舞うのですが、過信は禁物で、システムには限界もあります。そこを正しく理解することが大切でしょう。